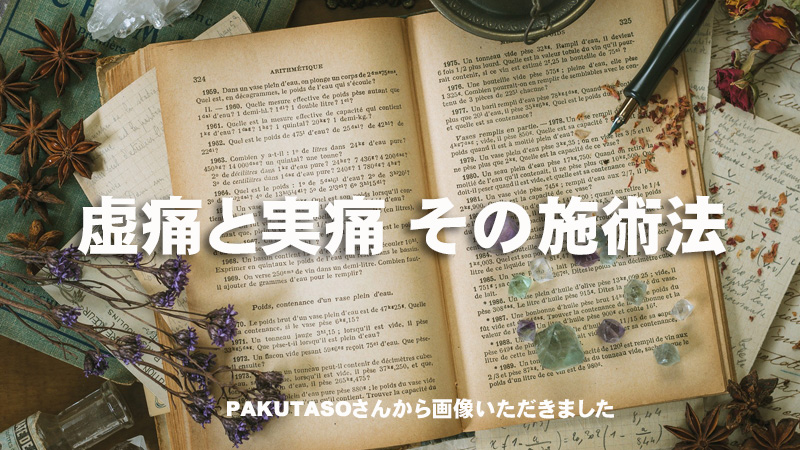
鍼灸といえば痛みに効くと思われますがこの痛みの判別と施術法が案外難しものです。
痛みを大雑把に、虚痛と実痛に分けます
実痛はそれほど難しい手技はいらないかもしれません。熱っぽく腫れていたり比較的新しい症状で痛みもはっきりしています。元気いっぱいの若い人やスポーツでのケガなどはほとんどこの範疇かと思います。難しく考えなくともぽんぽんと針を打てば何とかなるでしょう。
問題は虚痛のほう、重くだるいような夜中から痛み出したり少しさすると楽であったり、動き出すとましになる。患部は艶なく力ないし熱もない。またじっとりと汗ばんでいたりする。鍼灸院においでになる方はこちらが多いかもしれません。
この痛みに対して西洋医学的鍼灸ではどのような手技で対処するのかいんちょうさんはよく知りません。
いんちょうさんのところではこの虚痛で困っておられる方のほうが多いようです。そんな方がみえますと「いただき」といつも思ってしまいます。
痛みの改善、虚痛への施術法
虚痛を治すには当然ですが補法を行います。
鍼灸術はいかに理論づけできていても実際の手技が上手くおこなえるかということがポイントになるかとおもいます。
いんちょうさんがおこなう補法を簡単にまとめますと
銀か金の接触鍼で補す。あまり刺入しなくともよい。(豪鍼はテクニックが悪いと直ぐ瀉になってしまいがちなので注意)。また、ほとんどのものに適応するかと思いますが、灸を使うとよい、それも八分程度で火を消す(肌を傷つけないように。消すときのタイミングが難しい、押し付 けて消しては補にならない、挟みやや押して消すとよい)。 時には知熱灸での補法も用います。
もっと虚して発汗が収まりにくいものなどにはてい鍼で接触補する。
非常に重症のものにはベッドの掛けカバーのうえから接近補法をすることもあります。
よくある腰痛で背を伸ばせないものなどには座位で腰部の痛だるいところに接触補をすると即らくになることがおおいものです。
いずれにしても施術して肌に艶がでることや汗がひくこと、もちろん施術後に脈が改善されていること、そしてからだ全体の変化を見ることもたいせつなことかと思います。気を感じることができれば施術もやりやすくなります。
古典鍼灸術は面白い (^^)


コメント